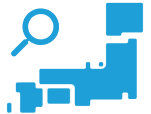新着記事
information-
協会からのお知らせ 2026/02/17
第22回 日本獣医内科学アカデミー学術大会 出展のお知らせ
2026年2月20日(金)〜22日(日)に開催される 第22回 日本獣医内科学アカデミー学術大会(JCVIM 2026) において、協賛企業展示ブースへ出展いたします。 また、2月21日(土)には、当協会 代表理事 丸田香緒里先生が「動物介護最前線」という演目で登壇予定 です。 往診・在宅医療という診療スタイルの可能性を学術の場からも発信してまいります。 学会にご参加予定の獣医師・愛玩動物看護師の皆さま、ぜひお気軽に協会ブースへお立ち寄りください。 往診という選択を、より現実的で持続可能なものへ。 今後も活動を続けてまいります。
-
活動報告 2026/01/12
活動報告 2025年
2025年の活動内容をまとめましたのでご報告します。 2025 活動報告ダウンロード
-
協会からのお知らせ 2025/10/14
松波総合病院「ペットおあずかりセンター」との協力について
こんにちは。往診獣医師協会です。このたび、岐阜県笠松町にある 松波総合病院 が開設した「ペットおあずかりセンター」 の取り組みに、当協会が協力することとなりました。 岐阜県羽島郡笠松町の松波総合病院は、日本初となる病院附設「ペットおあずかりセンター」(Your pet in hospital)を開設 地域医療連携推進法人内の海津市医師会病院に「ペットと一緒に入院できる病棟」(With Pet Ward)を整備 近年、ペットの寿命が伸びて高齢化が進む一方で、飼い主さん自身も高齢化し病気や体調の変化など健康上の不安を抱えるケースが増えてきています。ペットを大事にしている方ほど、自分が入院したら『この子はどうなってしまうのだろう』と心配が先に立ち、早期入院や早期治療の障壁になっていました。 松波総合病院のこうした取り組みにより、入院時にペットを自宅に残す心配が無くなると同時に、治療中もペットと触れ合うことができ、入院患者さんのストレスや痛みの軽減効果による早期治療、回復が期待できます。 ペットおあずかりセンター 急性期の治療や患者さんの評価は松波総合病院で入院して行います。その間は敷地内に新設された「ペットおあずかりセンター」で、医師等の許可があれば毎日面会可能です。 ペットと一緒に入院できる病棟の病室 ドッグラン 病状が安定したのちや評価後に海津市医師会病院へ転院し、ペットと同じ病室内で入院ができます。敷地内に開設されたドッグランの利用が可能です。(松波総合病院では、必ずしも海津市医師会病院へ転院する方だけを受け入れているわけではありませんが、海津市医師会病院へ直接入院することは出来ません。) 往診獣医師協会は、このセンターを利用する動物たちの健康管理や医療面での支援を行い、「人と動物が共に安心できる環境づくり」を一緒に進めていきます。 松波総合病院のホームページはこちら 今後も当協会は、動物医療の新しい形をサポートしながら、飼い主さんとペットが笑顔で暮らせる社会づくりに取り組んでまいります。 往診獣医師協会
飼い主のみなさま
to the owner往診動物病院とは
往診動物病院はこのようなお悩みのある方の力になれます
動物病院へ行く時間が確保できない、家を離れることができない
大型犬や多頭飼育で病院に連れていくのが困難
どうぶつさんが病院を嫌がる
生活環境も合わせて診てほしい
家で緩和ケアをしたい
家で看取りたい


飼い主様向けコラム
協会サポーターになる
往診獣医師協会は、往診を通して何歳になってもペットと共に暮らせる社会を目指します。
当協会の活動、理念に賛同いただける方のあたたかいご支援、お待ちしております。
協会サポータの皆様(50音順)
- 小毬
- 株式会社エステイナー
協働パートナー
collaborative partner往診獣医師協会として関わらせていただいている施設、企業様です

松波総合病院
賛助会員様
partners往診獣医師と連携しより良い診療体制を構築したい動物病院、理念に共感し
お力添えを頂ける協賛企業様です。

株式会社CoMediCs

エランコジャパン株式会社

株式会社上薬研究所

株式会社富士メディカルサービス

ゾエティス・ジャパン株会社

一般社団法人 獣医療サービス研究会

株式会社ユニコム

森久保CAメディカル株式会社

株式会社 V and P

株式会社12薬局

共立製薬株式会社

一般社団法人アニマルウェルフェア東京

日本獣医幹細胞培養上清液研究会

東栄新薬株式会社

ZENOAQ 日本全薬工業株式会社

株式会社ビルバックジャパン

株式会社ランス

テルコム株式会社

株式会社ファームプレス

防音犬小屋レンタくん

シグニ株式会社